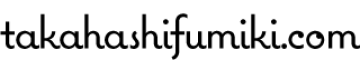タンスとタンスの間が、そんなに汚れていないとあって、進藤はイケるんじゃないかと思った。拳が入りそうなくらい中途半端な広さだったから、掃除が行き届くはずもないのだが、床は埃一つない。そこに美味そうな団子がころりと転がっている。つやつやして、いかにも美味そうだ。大方、トキ子がこしらえたまま、落としてしまったのだろう。いかにも、うかつなトキ子のしそうなことだ。料理教室で教えてもらったからとはりきって、手がおろそかになったのだろう。宿業だ――進藤は一人息巻いた。業ってヤツだ。おそらく、その団子は、トキ子がこねた中で一番美味いものだったろう。人生ってのはそういうもんだ。一番もっちりした団子が零れ落ちて、しかも家具の隙間で誰にも気付かれないまま、ある。それが人生だ。そういうもんだ。
進藤は手を伸ばした。団子まであと少しというところで、右の頬がタンスにつっかえた。団子は、いや、人生はすぐそこにあった。
結局、進藤は台所からお玉を取ってきて、団子を取ることに成功した。その隙間はこの上なく綺麗だったが、やはり口に入るものだからと思い直し、台所に立って洗った。スポンジに洗剤を滴らして、こんなに泡立つのか――などと驚きながら、お玉を執拗にこすった。もうこれ以上はできないというぐらい、汚れを落とした。トキ子は大変だな――などと思いながら、進藤は楽しくお玉をラックに入れた。箸でぎゅうぎゅうになった僅かな隙間を押し退けて、お玉はラックに収まった。一仕事終えた進藤は、団子を一口に頬張った。パサパサして、不味い団子だった。
午睡に入って目覚めてみると、進藤の腹はぐるぐるしていた。どうやら団子のせいだととりあえず悔やんでみても、吐いたり下痢をしたりではいかにも負けたようだ。とりあえず、我慢した。胃がめくれるような気がしないでもないが、何とかなりそうな気がしないでもない。搖蕩うときは、信じた者勝ちだ。這いつくばったまま、居間の新聞置き場を選んだ。まず訃報を確かめ、4コマ漫画を読み、東京面へ移るというのが進藤の流儀だった。
「あ」
と、進藤は呻いて、今日がサマージャンボの当選者発表日だったことを思い出した。確か、ジーンズのポケットから出して、冷蔵庫にマグネットで張り付けた気がする。そのまま虫のように這って、冷蔵庫の封筒を剥ぎ取り、新聞のあった場所まで戻ってみると、当たっていた。連番で買ったから、前後賞も当たっている。進藤はあまり驚かなかった。人生とはそういうものだ。進藤が味わった勝利は富にを勝ちえたことにあるのではない。富を得てなおそう思うことが勝利だ。お玉を洗ったのがよかった。あのときお玉を洗っていなかったら、三億円と供にある人生に押し潰されていただろう。
少し考えて、トキ子には言わないことにした。いや、言わないというより、取っておく。いつかは言うかもしれないという可能性が、夫婦を夫婦に保つのだ。
進藤はお湯を沸かした。コーヒー豆の在所がわからなかったので、台所を引っかき回した。ケトルがヒイヒイと鳴いた。ようやくのこと、冷凍庫にあるのがわかった。挽いた豆を缶に入れて、凍らせてあった。缶はひんやりと心地良かった。何ということはない、まだ夏なのだ。進藤は熱いケトルの取ってを布巾で掴み、ドリッパーに注いだ。泥のような色をしたコーヒーができた。胃を浄化してくれそうな、暗い色だった。
トキ子が帰ってくるのは七時半だった。猛烈に具合が悪かった。腹が痛いどころではない。脂汗が出て、もう三回は吐いていた。とても、トキ子が帰ってくるまで保ちそうはない気になって、進藤は遺書を書いた。大したことはしてやれなかったのだ、せめて遺産ぐらい、という算段だ。進藤は這うようにして駅前まで出て、水性ボールペンを買った。いつもの九八円のものではなく、万年筆を模した三百円のものだった。
机に向かって遺書を書いていると、いくらか気持ちが落ち着いた。夫婦になるまでの紆余曲折が身体を癒してくれるような気がした。雑記帳にしていたA4ノートの十五ページ目に遺書を書き終えると、進藤は眠りについた。
物音に起こされて、進藤は、あ、死んだ――と思った。自分で自分の身体見つめていた。幽体離脱というヤツだ。団子で死ぬとは。
まったく、と歯噛みような思いでいたら、やっぱり夢で、もう一度目が覚めた。台所でトキ子洗い物をしていた。具合はだいぶ良くなっていた。
「あ、起きた? ご飯は?」
トキ子は手を拭きながら進藤の方へ向かってきた。偉業をみれられてはまずい。進藤は机に飛びつき、慌てて隠すようにした。
「なによ、エロ動画でも見てるの?」
「いや、ポルノ小説を書いていた」
「小説? なにそれ? あんた、本読まないじゃん」
「自分の読みたいものを書くって決めた」
「何よ、変なの。会社休んでも、エロ小説書くしかないの」
トキ子は少しぷりっとしてみせたが、そのまま二人分の夕食の支度を始めた。八時半だった。とうに済ませてもいいはずが、待っていたのだ。可愛い女だ――と、進藤は食卓に向かった。ニラの安い季節だった。
久しぶりの有給はどうだった、と聞かれ、あまり回らない頭で、進藤は自分の人生を振り返った。この十年、働きづめに働いて、貯めに貯めた有給をまとめて取った日々が、変な団子と宝くじに当たって、遺書を書きかけたところで終わろうとしている。
「そういえば、あの団子はどうしたんだ? 作ったんか?」
「団子?」
トキ子が尋ね返すので、冷や汗がしたたり落ちた。
「お前じゃなけりゃ、誰だ?」
「誰だ、って、何キレてんのよ? しかも、団子って」
トキ子は大人しい顔に嘲り笑いを浮かべた。それがなおさら見下して見える。
「お前、団子作んなかったか? こんぐらいの」
親指と人差し指で○を象ると、トキ子はそれを下から覗き込むようにして、嘲り笑いを極めて見せた。
「はあ? 団子なんて、あんたと付き合ってから一回も作ったことないわよ。小学校の家庭科が最後よ。しかも、団子じゃなくて白玉だからね」
進藤は急に気持ち悪くなって、吐いた。うっすらと血が混じっていた。
「ちょっと何、あんた、それ?」
トキ子が叫んだ声が腹に響いて、もう一度えずいた。生温い吐瀉物を手に受けてみると、さっきよりもずっと赤い血が混じっていた。トキ子は悲鳴を上げた。
「ちょっと、あんた、どうしたの!」
頭からすっと血が引いて、進藤は倒れた。
今どんな気分か、と聞かれたら、なんと答えようか。進藤はぼんやりと色んなことを考えようとした。走馬灯という言葉を信じていたのだ。が、悲しいぐらいに、何を答えようという問いだけが浮かんでくる。俺は芸能人か。腹立たしい人生だ。この世に別れを告げるというのに、答弁のことばかり。
「宝くじが……」
進藤は呻いた。それが最後の正義だと思った。一体、宝くじが当たったことを妻に言わずして死ぬとは何事だ。そんな言葉を呑み込んだまま墓に入るなどとんでもない。
「当たったんだ……」
進藤は声を絞った。彼自身、こんな痛切な声は聞いたことがなかった。
「当たったんだよ……」
もう一度、絞るように言った。
「え、何よ? 何食べたのよ!」
進藤は半ば絶望しながら、トキ子に対して憤った。こいつは何もわかっちゃいない――そんな不満を押し込めて、やっぱり宝くじと言おうか、それとも団子と言おうか悩んでいるうち、意識を失った。