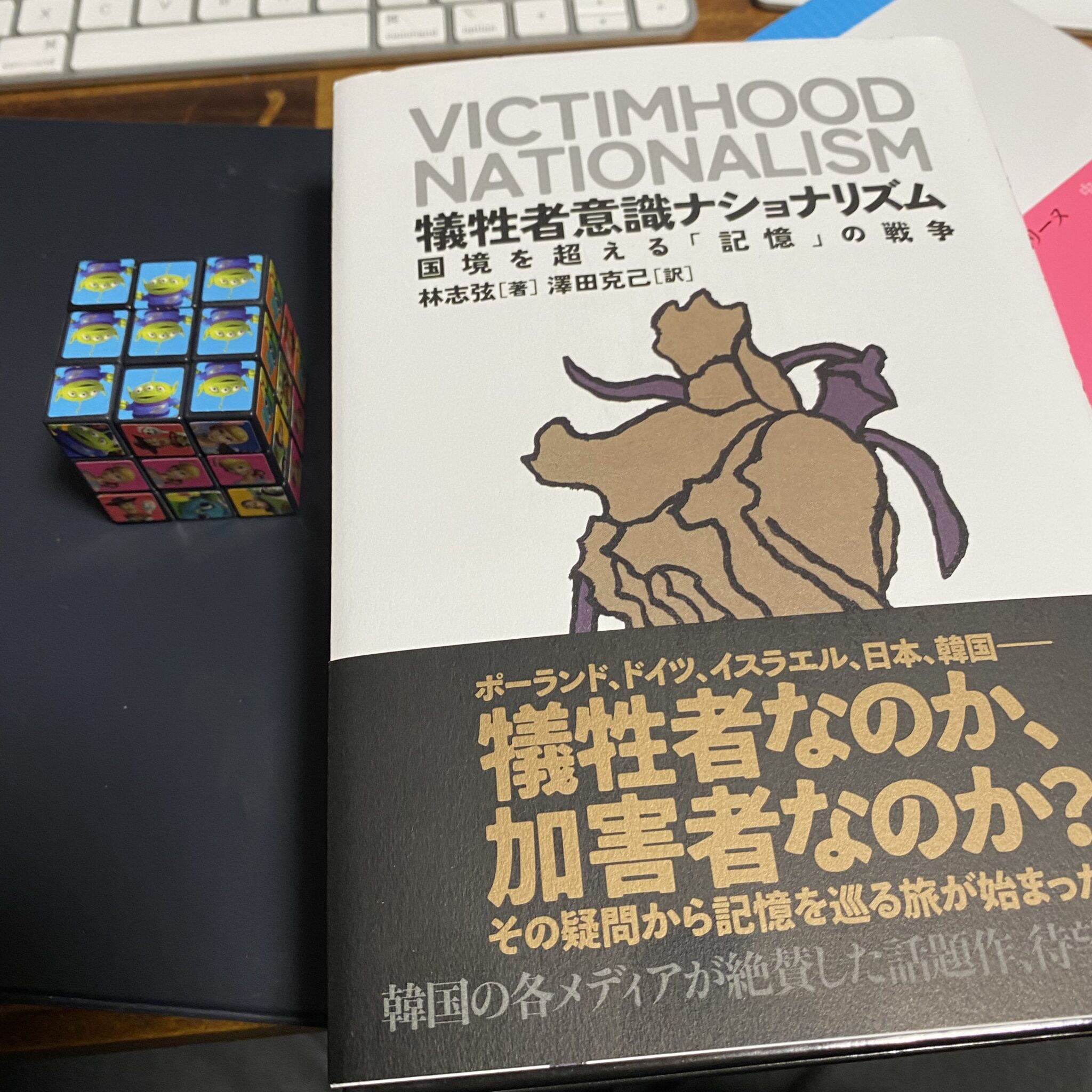世界的哲学者のイスラエル擁護
パレスチナ・ガザ地区のテロ組織ハマスがイスラエルで虐殺を行ったこと、そして、イスラエルがそのの報復として市民への虐殺をいまもなお行ったことは世界に衝撃を与えました。その事件に関して、イスラエルの報復が始まってすぐにドイツの哲学者マルクス・ガブリエルが寄せた論考がちょっと話題になりました。
無料登録すれば山陰中央日報で読めるのですが、ざっくり言うとこんな感じの主張です。
- ハマスのやったことはひどい
- 多くの人(国連など)は反ユダヤ主義を掲げるハマスの罠にハマっている。イスラエルの防衛行動は自衛であるのに、虐殺に見せかけている
- 反ユダヤ主義を広めてはならない
上で紹介した河野真太郎さんのツイートでもそうなのですが、ガブリエルの主張はいくつかの点であまり分析的とは言えない、というより、日本でも人気の世界的哲学者がそんなこと言っていいのか、という驚きがありました。
- イスラエルは1947年の建国以来パレスチナの土地を奪い続けており、ガザ地区からパレスチナ人をデッド・オア・アライブで追い出そうとしている。明らかに虐殺である。
- しかけたのはたしかにハマスが先だが、イスラエルの報復はその被害を圧倒的に上回っており自衛とは呼び難い。この気に乗じてパレスチナを殲滅しようとしているのでは。
- ハマスはガザ地区の政府ではあるが、パレスチナ全体の政府ではないので、民間人は関係ない。
などがガブリエルの主張に対する反論としてあり得るのですが、それはそれとしてタイムライン上で関係しそうな書籍として『犠牲者意識ナショナリズム』を紹介されました。
『犠牲者意識ナショナリズム』の内容
本書は韓国人の林志弦によるもので、第二次対戦後の犠牲者たちの意識の変容を「記憶のグローバル・ヒストリー」として捉えたものです。要するに、ホロコーストとか従軍慰安婦とかの「被害」を人々がどのように受け止め、共有してきたか、という本ですね。この本の面白いところは著者が「被害者」側の韓国人でありながら、被害の語られ方についてかなり公平な見方を試み、なおかつ日本の右傾化状態を認めつつも韓国と日本のナショナリズムが負の共生関係にあることを看破していることです。
たとえばホロコーストというのは、戦後はあまり知られていませんでした。それが1970年代ぐらいから「とんでもない虐殺があった」ということが周知の事実となり、ドイツの戦後責任の方向性が決定します。そして、第二次世界大戦の代表的被害国であるポーランドでは「第二次世界大戦の被害者は我々」というアイデンティティが築かれたにもかかわらず、実はポーランド人が積極的にユダヤ人を殺していた(これをポグロムと呼びます)ことが明らかになります。これがだいたい1990年代以降。そうするとポーランド人としては「一番の被害者は自分たち」というアイデンティティが揺らいでしまうわけです。このため、その事実を受け入れるために国民を巻き込んだ議論が巻き起こり、陰謀論なども闊歩しはじめます。これは日本の「南京大虐殺はなかった」「従軍慰安婦は志願性だった」などの主張とも呼応しますね。
僕は子供を叱るときに「被害者ムーブすんな」とよく言うのですが、自分が間違ったことをしたときに「実はその間違いは他の人によって引き起こされた」「こんなにも被害が大きい」というような、責任転嫁をすることは人間の生まれ持っての知恵という感じがします。また、被害者は訴えを強化することでより有利に立てるわけですね。この意地悪な洞察によって「記憶の戦争」がいまも続いているというのが本書の主張の一つです。本書の扉辞にもそれはあらわれていますね。
かつてユダヤ人は、財産や専門的職業、社会的地位、国際的ネットワークのために嫉まれる対象だった……。
今日の彼らは、死体焼却炉のために嫉まれている。
――ヴィトルト・クーラ
面白いのはこの犠牲者意識の変容がどのような経路をたどるか、ということです。本書では次のような変遷が章立てで語られます
- 昇華 被害者が国民的・民族的記憶に変わる瞬間。たとえば、国家の裏切り者であった「脱走兵」が「戦争の犠牲的英雄」に変わるパターンなど。
- グローバル化 被害はその当事者である民族や国家を超えて連帯していきます。これは『アンネの日記』が日本でめちゃくちゃ人気だというような事例を交えつつ、当事者の被害がグローバルに強化されていく事例が紹介されます。
- 脱歴史化 戦後からしばらく経つと、被害者の言説を加害者が持つようになります。これは耳が痛い話ですが、日本への原爆投下などですね。日本の敵国からすれば「自分たちで戦争起こしたんだから自業自得でしょ」というのはわりと普通の見方でしょうが、我々日本からすれば「原爆の被害がどれだけ悲惨か」を訴えることで自分たちの加害を少し軽減できるのでは、という目算が経ちます。そして、その「原爆の被害を訴える」という行動が冷戦構造下における東側陣営に利用されたことも興味深いですね。この本を読んでいる最中に長崎の原爆記念館に行ったので、興味深かったです。
- 過剰歴史化 被害者は自分たちの被害がいかにひどかったかを訴え続けることによって、より多くの対価を得られるので、当然ながらもったり隠したりします。「いいことも悪いこともした」「ひどいこともしたし、ひどいこともされた」という状況を「いいことをした」「ひどいことをされた」にすることで、自己正当化を図るわけですね。ここでは従軍慰安婦、ポーランド、イスラエルなどが事例に挙げられます。
- 併置 二つのことなる被害を並立させ、「これはあれと同じだ」と並べて見せることです。これは情報の普及によって可能になります。具体例としては長崎のコルベ神父が挙げられています。コルベ神父は被爆前の長崎で布教活動をし、ヨーロッパに戻ったあとアウシュビッツに収容され、ガス室に送られる同胞の身代わりとなったことで聖人となります。しかし、ナチスによるユダヤ人虐殺と原爆投下は脱歴史化で触れたとおり、ちょっと文脈が違うのですが、併置することで「なんとなく同じもの」という認識が生まれます。これまた長崎で大浦天主堂にいったので感慨深かったです。
- 否定 これは脱歴史化・過剰歴史化とも関係するのですが、積み上げられてきた被害者としてのアイデンティティを脅かすものは否定されます。ポーランドのポグロムの事例もそうです。ここでもやはり陰謀論が暗躍します。個人的には韓国に「光州事件はCIAと繋がった北朝鮮の謀略」という陰謀論があるようですね。
とまあ、こんな感じで非常に読み応えがありました。
感想
日本人は戦争加害者なので、かなり辛い読書にはなりますが、読んで損はないです。ホロコーストといえば、終戦後すぐに戦争中の大犯罪と認定されたと思ってしまいますが、その受容は一筋縄ではなく、いまもなお変遷し続けているわけですね。現在、ガザで戦争を行なっているイスラエルの要人が口にする「ホロコースト」という響きは注意して聞く必要がありそうです。終わり。